経理代行サービスとは?依頼可能な経理業務や利用するメリットなどを解説
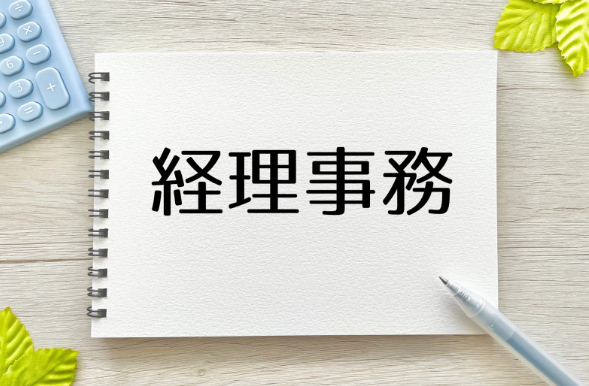
経理代行サービスとは?依頼可能な経理業務や利用するメリットなどを解説
本記事では、経理代行について解説します。経理代行とは、経理業務の一部またはすべてを、サービス提供会社に委託することを指します。
とはいえ、経理代行サービスで具体的にどのような業務を任せられるのか、分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで本記事では、経理代行サービスに依頼できる主な業務の種類や、その詳細について解説します。
また、経理代行サービスを利用するメリットや、利用する際の注意点についても紹介します。経理代行の依頼を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
経理代行とは?

経理代行とは、自社で行っている経理業務を外部に委託し、処理してもらうことを指します。
経理業務には、専門的な知識が求められる分野や、正確性が重視される業務が少なくありません。
経理代行サービスは、税理士事務所や会計事務所をはじめ、経理業務に特化したアウトソーシング企業などが提供しています。
自社で行うには負担の大きい経理業務を外部に委託することで、社内のリソースをより重要な業務に振り向けたり、従業員の負担を軽減したりすることが可能になります。
経理代行サービスに依頼できる業務
経理代行サービスでは、さまざまな経理業務を依頼することが可能です。ここからは、その中でも代表的な業務と、その内容について詳しく解説します。
記帳業務
経理代行サービスでは、経理業務の中でも基本的な業務のひとつである記帳業務を代行してもらうことができます。
記帳業務とは、日々の取引や経費の支払い、預貯金の動きなどを、簿記の手順に従って帳簿に記録する業務です。
この業務は、税金の申告や収支の把握、決算書類の作成などにも関わるため、非常に重要です。
しかし、記帳業務には複式簿記の知識が求められるため、対応できる人材の雇用や従業員への教育が必要になります。
経理代行サービスを利用することで、採用や教育にかかるコストを削減することが可能です。
経費精算
経費精算も、経理代行サービスで対応してもらうことができます。通常の経費精算とは、出張や営業活動に伴い、従業員が一時的に立て替えた費用を精算する業務です。
経理代行サービスでは、申請内容や金額のチェックだけでなく、領収書の整理といった初期段階から代行してもらえる場合もあります。
給与計算
従業員に支払う給与額の計算も、経理代行サービスに含まれる業務のひとつです。
給与計算は、従業員の生活に直結し、会社への信頼にも関わるため、経理業務の中でも特にミスが許されない作業です。
さらに、給与計算は毎月発生するルーティン業務である一方で、労働保険や社会保険、住民税や所得税など、幅広い専門知識が求められます。
このように、正確性と専門性が要求される煩雑な給与計算業務を経理代行サービスに任せることで、社内の負担を軽減できます。
支払い・振り込みの代行
支払い・振り込みは一見すると単純な作業に思われがちですが、実際には手間と時間がかかる経理業務のひとつです。
加えて、ミスが発生すれば取引先からの信頼を損なう可能性があるため、高い正確性が求められます。
経理代行サービスを活用すれば、支払い・振り込みの実行だけでなく、振込先の登録や振込内容の確認なども代行してもらえます。
売掛金・買掛金管理
企業間の取引では、売掛や買掛といった掛売りが行われることが一般的です。
売掛金や買掛金については、金額の誤りや支払い期限の超過、請求漏れなどがないか、常に確認する必要があります。
こうした管理を怠ると、取引先からの信頼を損なったり、金銭的な損失を招いたりする可能性があるため、日頃から適切なチェックと対応が求められます。
経理代行サービスに売掛金・買掛金の管理を依頼することで、こうしたリスクの発生を未然に防ぐことが可能です。
請求書発行
経理代行サービスに依頼できる業務のひとつに、請求書の発行があります。請求書発行は、経理業務の中でも特に手間と時間がかかる作業とされています。
具体的には、取引内容や請求金額の確認、請求書の作成・発行など、複数の工程が必要です。さらに、紙の請求書を発行する場合には、印刷や封入、発送といった作業も発生します。
経理代行サービスを活用すれば、こうした煩雑な作業を外部に委託することができます。その結果、コア業務にリソースを集中させたり、業務の効率化を図ったりすることが可能です。
年末調整:税理士業務
年末調整は、毎年11月から12月頃にかけて行われる、毎月の給与から天引きされている所得税の過不足を精算するための業務です。
この業務は、各従業員ごとに対応が必要なうえ、扶養控除等申告書や給与台帳など多数の書類を扱うため、作業が煩雑になりがちです。
さらに、住宅ローンなどの税額控除や生命保険の加入などに伴う所得控除も考慮する必要があり、担当者の負担は大きくなります。
こうした複雑な年末調整業務も、経理代行サービスに依頼することが可能です。
ただし、年末調整は税金に関わるため、税理士の独占業務とされています。そのため、税理士事務所を併設または提携している経理代行サービスを選ぶことが重要です。
決算、申告:税理士業務
決算処理も、経理代行サービスが対応できる業務の一つです。
決算とは、一定期間における企業の収入や支出を集計し、利益や損失を確定させる作業を指します。
毎年実施される本決算のほか、半年ごとの中間決算、毎月の月次決算なども含まれます。
なかでも本決算は、法人税などの申告業務と密接に関わっています。
本決算によって確定した利益や損失をもとに納税額を算出し、税務署に申告する必要があります。
なお、申告業務の代行は、税理士または税理士法人のみが対応可能な「税理士の独占業務」に該当する行為です。
申告業務を委託する場合は、税理士事務所または税理士法人に依頼することになります。
そのため、申告をスムーズに行うためには、税理士事務所等が提供する経理代行サービスを選ぶか、税理士事務所等を併設または提携している経理代行サービスを選ぶ必要があります。
経理代行の依頼先

経理代行を依頼できるのは、主に税理士事務所・会計事務所、または経理代行会社などです。以下は、それぞれの依頼先の詳細と特徴です。
税理士事務所・会計事務所
税理士事務所や会計事務所には、会計や税務申告を専門とする税理士が在籍しています。
経理業務の中には、年末調整や申告など、税理士の独占業務も含まれています。
これらの業務は、税理士事務所や会計事務所に依頼すれば、問題なく対応してもらうことが可能です。
記帳業務から決算申告までを一括で依頼したい場合におすすめです。
ただし、税理士事務所や税理士法人は、経理代行サービスに対応していない場合もあるため注意しましょう。
経理代行会社
経理代行をサービスとして提供している会社も、選択肢のひとつです。記帳や帳簿作成、月次決算などの業務を代行してもらうことができます。
なお、年末調整や申告などの業務は税理士の独占業務にあたるため、税理士事務所等でなければ依頼できません。
これらの業務も含めて代行を依頼したい場合は、税理士事務所等を併設または提携しているかを確認しましょう。
経理代行サービスを利用するメリット

経理代行サービスを利用するメリットはいくつかあります。ここからは、具体的なメリットとその詳細について解説します。
コア業務にリソースを割ける
経理業務を外部に委託することで、社内のリソースを他の業務に振り向けることが可能になります。
経理は企業にとって欠かせない業務ではあるものの、利益拡大や企業成長といった本質的な部分には直接関与しません。
経理代行サービスを利用すれば、経理業務の負担を軽減し、戦略策定や経営判断といった重要な業務にリソースを集中させることができます。
また、人手が不足している企業においては、経理担当者が少ない場合や、他の業務と兼任しているケースも少なくありません。
そうした状況でも、経理代行を活用することで、コア業務により多くのリソースを割けるようになります。
人手不足の解消に繋がる
経理代行サービスを利用すれば、外部のリソースを活用できるため、人手不足の解消につながります。
経理業務は専門性が高く、人材の確保や育成が難しい傾向にあるため、人手不足に陥りやすいです。
しかし、経理代行サービスを活用することで、こうした課題を効果的に解決することができます。
また、経理代行サービスは一時的、あるいはスポット的に利用することも可能です。
そのため、慢性的に人手が不足している企業だけでなく、月末や月初といった経理業務の繁忙期に一時的にリソースを補いたい場合にも有効です。
人材採用・育成の負担が減る
経理は、簿記の知識をはじめ、税法や社会保険など幅広い分野の知識が求められる、専門性の高い業務です。
そのため、即戦力として活躍できる人材の採用は難しい傾向にあります。また、社内で人材を育成するにも時間やコストがかかる点も課題です。
経理代行サービスを利用すれば、必要なタイミングで必要な分の経理業務を柔軟に依頼することができます。
自社で人材を抱える必要がなくなるため、採用や育成にかかる負担を大幅に軽減することが可能です。
各種コストを削減できる
経理代行サービスの利用は、各種コストの削減にもつながります。自社で経理担当者を雇う必要がないため、人件費や育成にかかるコストを抑えることが可能です。
さらに、会計ソフトを代行会社側で用意してもらう場合には、経理業務に必要なパソコンや会計ソフトなどの設備を自社で用意する必要もないため、これらにかかる費用も削減できます。
不正防止の効果が期待できる
経理業務は、その専門性の高さから、業務内容がブラックボックス化しやすい傾向にあります。
そのため、社内の経理担当者による横領や改ざんなどの不正行為が発生しても、発見が遅れることが少なくありません。
経理代行サービスを利用して経理業務を外部に委託すれば、第三者の目が加わることで財務状況の透明性が高まります。
これにより、社内でのブラックボックス化を防げるだけでなく、不正の防止や早期発見にもつながります。
経理業務の属人化を防止できる
経理業務は、専門的な知識や正確な作業が求められるため、人材の確保や育成に手間がかかりがちです。
しかし、同じ人材に長期間経理業務を任せ続けると、属人化のリスクが生じます。
属人化がリスクとなるのは、病気による長期休職や突然の退職などが発生した際に、経理業務の進行が滞る可能性があるためです。
経理代行サービスを利用すれば、契約に基づいて安定的に経理業務が遂行されます。特定の人材に依存することなく、属人化に伴うさまざまなリスクを回避できます。
法改正に対応しやすくなる
経理代行サービスを利用するメリットのひとつが、法改正への対応がしやすくなる点です。経理関連の法律は頻繁に改正される傾向があります。
たとえば、2022年には電子帳簿保存法の改正が行われ、2023年にはインボイス制度が導入されました。
こうした法改正があった場合には、トラブルやペナルティを回避するために、迅速かつ適切な対応が求められます。
自社で対応するとなると、最新情報の収集や業務への反映に手間がかかり、経理担当者の負担が大きくなりがちです。その点、経理代行サービスを活用すれば、こうした負担やリスクを軽減することが期待できます。
経理代行サービスを利用する場合の注意点

経理代行サービスを利用する場合は、いくつか注意するべき点もあります。以下は、代表的な注意点とその詳細です。
情報漏洩のリスクがある
経理代行サービスを利用するにあたっては、自社の重要な情報を外部に提供する必要があります。たとえば、財務データや従業員の個人情報などが該当します。
こうした情報を外部に渡すことにより、情報漏洩のリスクが高まる点には注意が必要です。リスクを抑えるためには、経理代行サービスを提供する会社のセキュリティ体制を確認することが重要です。
具体的には、プライバシーマークやISMSの取得状況を確認したり、秘密保持契約の締結が可能か確認したりしましょう。
自社にノウハウや知識が蓄積されない
外部に経理業務を委託する以上、自社に経理ノウハウや知識が蓄積されにくくなる点には注意が必要です。
また、自社で経理業務を行わなくなることで、それまで社内に蓄積されていた知識やノウハウが徐々に失われてしまう可能性もあります。
将来的に経理業務を自社で完結させたいと考えている場合や、予算の都合で将来的にアウトソーシングを終了する可能性がある場合には注意しましょう。
対策としては、内製化の支援を行っている経理代行サービスを選ぶことや、委託する業務の範囲を限定することが有効です。
社内の人材育成が滞る可能性がある
経理代行サービスを利用することで、社内の人材育成が滞る可能性があります。これは、経理業務を外部に委託することで、社内の経理担当者に対して割くリソースが減少するためです。
将来的に経理業務を自社で完結させたい場合や、社内で経理担当者を育成したいと考えている場合には、委託する業務の範囲を絞ることが重要です。
詳細な進捗状況が分かりづらい
ビジネスシーンにおいては、業務の進捗状況を正確に把握し、それに応じた適切な対応を取ることが求められます。
しかし、経理業務を外部に委託している場合、業務の進捗や数値の変化をリアルタイムで把握しづらい傾向があります。
そのため、経理代行サービスを利用する際は、細やかな連携が可能かどうか、委託先のサポート体制を事前に確認しましょう。
今よりもコストが増える可能性がある
自社の経理業務の状況や委託する業務の量によっては、現在よりもコストが増加する可能性があるため、注意が必要です。
たとえば、経営者自身が経理業務を行っていた場合、これまで実質的にコストがかかっていなかった部分に、新たな費用が発生することになります。
さらに、税理士業務の年末調整や給与計算などを含むすべての経理業務を外部に委託した場合、自社で経理担当者を雇用した方が、結果的にコストを抑えられるケースもあります。
まとめ
本記事では、経理代行サービスに依頼できる業務内容や依頼先の種類、サービスを利用するメリット、そして利用時の注意点について解説してきました。
経理代行サービスは、人手不足の解消や業務効率の向上といった効果が期待できる一方で、社内ノウハウの蓄積が進まないことや、コスト増加といったリスクも伴います。
そのため、経理代行サービスは自社の状況や目的に応じて、適切に活用することが重要です。導入を検討している方は、ぜひ本記事を参考に、自社にとって最適な選択をしてみてください。


