【2025年最新版】経理代行サービスとは?料金相場・依頼できる業務・メリットデメリットを徹底解説

経理代行サービスとは、企業が本来社内で行っている経理業務を、外部の専門会社や税理士事務所に委託する仕組みです。
人手不足やコスト削減のニーズが高まるなか、中小企業から上場企業まで幅広く利用が拡大しています。
一方で「料金はどのくらいかかるのか?」「税理士に依頼するのとどう違うのか?」「メリットとデメリットは?」など、不安や疑問を抱える方も多いでしょう。
本記事では、経理代行サービスの基本から、依頼できる業務範囲、料金相場、導入のメリット・注意点、選び方のポイントまで徹底解説します。
経理代行を検討中の経営者・経理担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
経理代行サービスとは?依頼できる業務内容と税理士の役割

経理代行サービスとは、記帳や経費精算、給与計算、請求書発行などの経理業務を、外部の事務所やアウトソーシング会社が代行するサービスです。
専門知識と豊富な実績を持つプロフェッショナルが、日々の煩雑な業務を効率的に処理してくれるため、社内の人材がより重要な業務に専念できるようになります。
経理代行サービスが対応できる業務は多岐にわたります。
ここでは代表的な業務を、具体的な内容と合わせてご紹介します。
記帳代行(日々の取引の仕訳・データ化)
経理代行の最も基本的な業務です。日々の取引の仕訳を会計ソフトに入力し、会計帳簿を作成します。
【具体例】
- 預金通帳のコピーやクレジットカードの利用明細
- 領収書や請求書、売上伝票などの証憑
- 現金出納帳
これらの書類を代行業者に送付するだけで、専門家が正確な記帳を行います。
freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを活用することで、リアルタイムでのデータ共有も可能です。
経費精算代行
従業員が立て替えた経費の申請内容をチェックし、精算業務を代行します。
【具体例】
- 従業員からの経費申請内容の確認
- 領収書のデータ化・整理
- 精算データの集計と振り込み依頼
細かな作業が多いため、上記の業務を代行することで社員の負担を大きく軽減し、生産性を向上させることができます。
給与計算・勤怠管理
従業員に支払う給与額の計算と、それに伴う勤怠管理業務です。
【具体例】
- 基本給、各種手当、残業代の計算
- 所得税、社会保険料、住民税の算出と控除
- 給与明細の発行と送付
給与計算は毎月発生し、法律改正への対応も必要となるため、専門家に任せることでミスなく安定した業務遂行が可能です。
支払い・振り込み代行
買掛金や経費、給与などの支払いを、指定された期日までに代行します。
【具体例】
- 支払いリストの作成と最終確認
- インターネットバンキング等を利用した振り込み作業
単純作業に見えますが、振り込みミスは取引先との信用問題に直結するため、専門家に任せることで安心感が増します。
売掛金・買掛金管理
企業間の取引で発生する売掛金(売上債権)と買掛金(仕入債務)の管理です。
【具体例】
- 請求書の作成と発送
- 期日までの入金確認と消込作業
- 支払いスケジュールの管理
キャッシュフローを健全に保つ上で不可欠な業務であり、代行を依頼することで債権・債務の状況を常に正確に把握できます。
年末調整・確定申告
この業務は、税理士の独占業務です。
経理代行会社は直接代行することはできませんが、多くの会社が税理士事務所と提携しているため、ワンストップで対応してもらえるケースがほとんどです。
- 年末調整: 各従業員の所得税の過不足を精算する業務
- 確定申告: 企業の年間所得を確定し、納税額を計算して税務署に申告する業務
依頼する際は、税理士との連携体制があるか、また追加費用が発生するかどうかを事前に確認しましょう。
経理代行サービス導入を検討すべきタイミングと判断基準
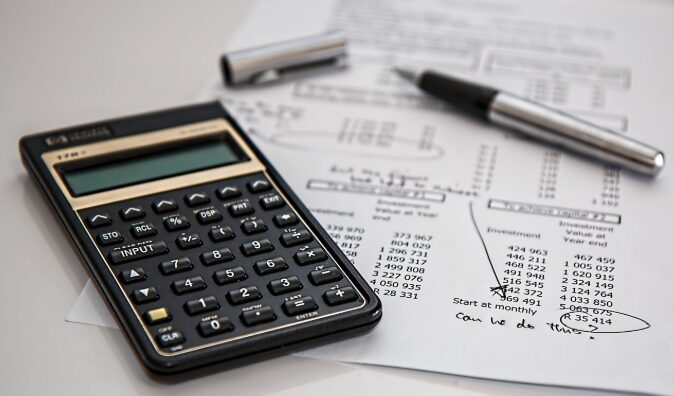
経理代行サービスが自社に必要かどうかは、企業規模や業務負担によって異なります。以下のチェックリストで導入の判断基準を確認しましょう。
経理業務に割くリソースがない
- 経営者自身が経理を兼任しており、本業に集中したい
- 従業員が経理業務と他業務を兼任しており、負担が大きい
経理の専門知識を持つ人材がいない
- 経理の経験者がおらず、採用や育成に時間やコストをかけたくない
- 簿記の知識や税務、法改正への対応に不安がある
経理業務の効率化・自動化を進めたい
- 紙の証憑が多く、データの入力作業が煩雑になっている
- 給与計算や請求書発行などのルーティンワークを効率化したい
上記に一つでも当てはまる場合は、経理代行サービスの導入を検討する価値があるでしょう。
経理代行サービスを利用するメリット

導入前に知っておくべき、経理代行のメリットを詳しく見ていきましょう。
1. コア業務にリソースを集中できる
経理代行サービスを利用すれば、経理の負担が軽減され、営業活動や経営戦略の立案、新サービスの開発など、利益に直結するコア業務にリソースを集中できます。
2. コスト削減につながる
経理担当者を一人雇用する場合、人件費(給与、社会保険料、賞与など)や採用費、教育費、さらにPCや会計ソフトの費用など、多くのコストが発生します。
経理代行を利用すれば、これらのコストを大幅に削減し、必要な業務を必要な分だけ依頼できるため、コストパフォーマンスが高い選択肢となります。
3. 専門家による安心感と正確性の向上
経理代行会社のスタッフは、経理・会計のプロフェッショナルです。
簿記や税務に関する専門知識が豊富で、最新の法改正にも迅速に対応します。これにより、ヒューマンエラーによるミスや、税務上のトラブルを未然に防ぐことができます。
4. 経理業務の属人化を防ぐ
特定の社員に経理業務が集中すると、その社員が退職したり休職したりした場合、業務がストップしてしまうリスクがあります。
経理代行サービスは、契約に基づき安定的に業務が遂行されるため、属人化によるリスクを回避し、事業の継続性を高めます。
5. 不正防止の効果が期待できる
社内で経理業務が完結していると、担当者による不正行為が発覚しにくい場合があります。
経理業務を外部に委託することで、第三者の目が入り、財務状況の透明性が高まります。
これは、不正の抑止力となり、早期発見にもつながります。
6. 法改正への対応が容易
電子帳簿保存法やインボイス制度など、経理に関する法改正は頻繁に行われます。
経理代行サービスを利用すれば、最新の法改正に迅速に対応でき、ペナルティやトラブルのリスクを軽減できます。
7. ITツール活用による効率化
クラウド会計ソフトや経費精算システムと連携できる経理代行サービスなら、入力作業を大幅に効率化できます。
紙の証憑が多い企業でも、スキャンや電子化を通じて業務改善が期待できます。
経理代行サービスを利用するデメリットと注意点

1. 情報漏洩のリスク
会社の重要な財務データや従業員の個人情報を外部に提供するため、情報漏洩のリスクはゼロではありません。
【対策】
- プライバシーマークやISO27001(ISMS)などの認証を取得しているか
- 秘密保持契約(NDA)の締結が可能か
- 情報管理体制やセキュリティポリシーが明確か
これらを事前に確認し、信頼できる会社を選びましょう。
2. 社内にノウハウが蓄積されない
外部に業務を任せるため、自社で経理業務を行う機会が減り、ノウハウが蓄積されにくくなります。
将来的に内製化を考えている場合や、急な自社対応が必要になった場合に困る可能性があります。
【対策】
- 委託範囲を限定し、重要な業務は自社で管理する
- 定期的に進捗報告を受け、業務内容を把握する
3. リアルタイムでの進捗把握が困難
業務を外部に委託すると、自社で担当している場合と比べて、業務の進捗状況をリアルタイムで把握しづらくなります。
【対策】
- オンラインチャットやクラウドツールを活用し、密なコミュニケーションを取る
- 月次レポートなど、定期的な報告を義務付ける
4. コストが増加する可能性がある
経理代行の費用は、業務量や依頼する範囲によって大きく変動します。
これまで自社で経理を行っていた場合、費用が発生していなかった部分に新たなコストが加わるため、予想外の出費となる可能性もあります。
【対策】
- 複数の会社から見積もりを取り、料金体系を比較する
- 依頼する業務を明確にし、追加費用が発生しないか確認する
経理代行サービスの料金相場

経理代行サービスの料金相場は、現実には以下のような多様な要因で変動するため、一概に示すことは困難です。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 依頼する業務範囲 | 記帳代行のみか、給与計算や振込代行を含むかなど |
| 企業規模 | 従業員数に応じた料金が設定されている場合がある |
| 個人事業主/法人 | 個人事業主と法人では異なる料金体系の場合がある |
| 企業の取引件数 | 取引件数に応じた料金が設定されている場合がある |
基本的には、業務にかかる時間(稼働時間)に応じて料金が見積もられます。依頼する業務範囲や企業規模、取引件数などに応じて稼働時間も異なります。したがって、これらの状況を示して個別に見積もりを取らなければ料金の目安は把握できません。
あくまでも参考ですが、一般的に示されている相場を簡易な料金表にして紹介します。
| 代行業務の内容 | 相場 |
|---|---|
| 記帳 | 仕訳1件につき月額50~150円 |
| 給与計算・年末調整 | 月額1万円~ + 従業員1名につき1,500円 |
| 決算 | 年額10~30万円 |
| 丸投げ (フルアウトソース) | 月額5万円~50万円 |
なお、経理代行サービスを比較・選定する際、料金の安さだけを基準にすることはおすすめできません。経理代行サービスによって、コミュニケーションを含めた対応の早さや提案・サポートの質が異なるためです。サービス内容を総合的に考慮して比較しましょう。
料金の相場感を把握するためには、できる限り依頼内容を明確にしたうえで、複数の経理代行サービスから見積もりを取ることをおすすめします。
経理のアウトソーシングはやめとけと言われる理由とは?懸念事項と対策

経理代行サービスの利用には大きなメリットがある一方で、「経理のアウトソーシングはやめとけ」といった否定的な声があることも事実です。
このような声が挙がる理由と、それに対する具体的な対策を知っておくことで、安心して導入を進められます。
1. 税務申告は税理士法に違反するため対応できない
経理代行サービスは、一部の業務において法律上の制約を受けます。
税理士法第52条は、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行なってはならない」と定めています。税理士業務は以下の内容を含みます。
| 税理士業務 | 内容 |
| 税務代理 | 申告などの代理や代行 |
| 税務書類の作成 | 申告書等の作成の代理や代行 |
| 税務相談 | 申告等に関する課税標準等の計算に関する事項について相談に応じること |
記帳や売掛金・買掛金の管理、経費精算、給与計算の代行自体は、上記の税理士業務に該当しないため、税理士法違反の問題にはなりません。
しかし、申告書の作成(税務書類の作成)や申告(税務代理)、年末調整の代行は税理士業務に該当する可能性が高く、税理士資格または税理士との連携がない経理代行サービスでは対応できません。この点が「ワンストップで対応できない」として懸念材料となることがあります。
【対策】
税務申告まで依頼したい場合は、税理士事務所が運営する代行サービスを選ぶか、税理士と連携している代行会社を選ぶことが必須です。
契約前に、税理士業務の対応範囲と追加費用を必ず確認しましょう。
2. 社内で経理人材が育たない問題
経理業務を外部に委託(外注)すると、経理に関する知識やスキル、ノウハウが社内に蓄積されにくいというデメリットがあります。
社内の人材が実務に触れる機会が減るため、将来的に内製化を目指している企業にとっては大きな問題となります。
【対策】
経理業務の全部ではなく、一部の委託に留める、または代行サービスに業務フローの構築支援やマニュアル作成を依頼し、最終的に自社で運用できる体制を目標にすることで、ノウハウの喪失を防ぐことができます。
3. 機密情報の漏洩リスクへの対策が必要となる
経理代行サービスを利用する際は、自社の取引内容、従業員の給与、仕入れ価格など、企業経営に関わる重要な機密情報を提供する必要があります。
情報管理体制が不十分な代行サービスを利用した場合、情報漏洩のリスクは否定できません。
【対策】
経理代行サービスを利用する際は、機密情報の管理体制を徹底的に確認することが必要です。
信頼できる事業者であることを確認したうえで、秘密保持契約(NDA)を必ず締結しましょう。
経理代行サービスの選び方・比較方法

経理代行サービスを提供している事業者は数多く存在します。
自社に最適なサービスを選ぶためには、以下の基準をもとに比較検討を行うことが重要です。
対応する経理業務の範囲
経理代行サービス選びで最も大切なのは、依頼したい業務に対応しているかどうかです。
記帳や給与計算、請求書発行などの一般的な業務に加え、申告書の作成や税務申告といった税理士業務の対応が必要かどうかも確認しましょう。
また、基本料金に含まれる範囲とオプション対応の範囲を整理することで、正確な比較が可能になります。
料金体系と費用の明確さ
経理代行の料金は、業務範囲や依頼するボリュームによって大きく変動します。
- 基本料金に含まれる内容
- オプション料金の有無
- スポット依頼と月額契約の違い
これらを複数社で比較し、総合的なコストパフォーマンスを判断することが大切です。
サポート体制
経理業務を継続的に外部に委託する場合、スムーズな連携と信頼関係は欠かせません。
チャットやメール、電話などの対応手段、トラブル発生時のサポート体制、担当者の変更可否などを確認し、安心して任せられる体制かどうかを見極めましょう。
機密情報の管理体制
経理代行サービスでは、従業員の個人情報や財務データといった機密情報を扱います。
したがって、具体的なセキュリティ体制を確認することが必須です。
【確認すべき項目の例】
- オフィスの入退室管理
- データ受け渡しの方法
- データ暗号化やアクセス権限の設定
- ウイルス対策ソフトやセキュリティポリシーの有無
プライバシーマークやISO27001(ISMS)を取得状況は信頼性を判断するポイントになります。
導入実績・対応業種
これまでの導入実績や対応している業種を確認することも重要です。
自社と同規模・同業種の企業に導入実績があれば、スムーズな対応が期待できます。
経理代行サービス導入の流れと手順

経理代行サービスは、相談から契約、業務開始までの手順が整っているため、初めてでも安心して導入できます。
問い合わせ・無料相談
各社のウェブサイトから問い合わせ、無料相談を申し込みます。
このとき、自社の現状や課題、依頼したい業務を具体的に伝えます。
ヒアリング・見積もり
代行会社の担当者によるヒアリングを受け、正式な見積もりとサービスプランが提示されます。
複数社から見積もりを取り、料金や内容を比較検討しましょう。
契約・業務開始準備
内容と見積もりに納得したら契約を締結します。
秘密保持契約(NDA)も必ず結び、必要な書類や情報共有方法をすり合わせます。
問い合わせ・無料相談
各社のウェブサイトから問い合わせ、無料相談を申し込みます。
業務開始
合意したフローに基づいて業務がスタートします。
定期的な進捗報告を受けながら、必要に応じてコミュニケーションを取りましょう。
導入の際は、必ず複数の会社を比較し、自社に最適なサービスを選定することが成功のポイントです。
経理代行サービスで経理の悩みを解決しよう
経理代行サービスは、日々の記帳や給与計算、決算業務まで幅広く対応できる便利な仕組みです。
煩雑な経理業務を外部に任せることで、コスト削減や効率化を実現し、より重要な業務にリソースを集中できます。もちろんデメリットや注意点もありますが、選び方のポイントを押さえれば安心して導入できます。
経理の負担を減らし、事業の成長に集中するために、ぜひ経理代行サービスの活用を検討してみてください。


